中3の内申が出そろいました。
中2後期のものと比べて、一人あたり約3.5ポイントアップです。
なかには10ポイントあがった生徒も。
よく頑張りました。
とはいえ志望校の目標内申と照らしたときに、
全員が目標達成できたというわけではありません。
「5教科であと1ポイント良ければ…」
そういう生徒もいます。
2年後期からの1年間の流れをみたところだと、
技能教科に対して5教科の内申の伸びは比較的小さかったように思います。
たとえば、内申「5」を目指すとして、
中3前期中間テストで70点を取ってしまった場合、
残る前期期末テストや後期中間テストで90点近くを連続でマークしたとしても、
内申「4」で止まってしまうケースが目立っています。
一方では、前期中間テストから内申「5」に値する好成績を収めていれば、
最終的に「5」でゴールできる。
この分析から言えることは
「周りのエンジンがまだかかっていない前期の努力が大切だ」ということ。
早速中2生に向けてこの共有をしました。
「3年生になってから勉強の質を上げ始めるのはダメだ。勉強の質を高くした状態で3年生のスタートを迎えよう」
受験にはフライングなんて存在しませんので、
とにかく早く始めた人が圧倒的に有利です。
努力を後回しにせずに、今から向き合えるようにしましょう。
今週はヘリオス小学部のコンクールです。
火曜は4年生、木曜は2・3年生、金曜は5・6年生の本番です。
本番で結果を出すために、2週間前から練習を頑張っていました。
「テストがあるなら、子どもは当然に頑張って勉強するものだろう」
じつは私がこの仕事に就いたころはそう思っていましたが、
現場にたって、いつとはなしにそれは当たり前ではないことに気付きました。
何のために頑張るのか。テストで点数を取ったから何なのか。
自分の好きな事を我慢して勉強するには、それなりの理由が必要ですよね。
特にヘリオス小学部は中学受験をしないので、
勉強を頑張る理由がなかなか見つからないというケースもあると思ったのですが。
ところが、そんな不安をよそに
ヘリオス小学部の子たちは、目前のテストに向かってしっかり頑張れています。
これはすごいことだと思っています。
成績優秀者に名前が掲載されるのを目標にしている子も。
100点満点×5科目を目指す子も。
それは私の指導から、というよりは
周りの仲間からの影響が大きいのではないかと思います。
こんな環境の中で勉強できるのは幸せなことですし、
指導をしている身としても幸せを感じています。
各クラス、コンクールの結果返却は来週です。
11月22日(土)、23日(日)に後期中間テストの直前土日対策を行いました。
今回は、近隣と比べて日程が1週間早い井田中生のみが対象です。
教材の1周目はその時点でのできる問題とできない問題の「仕分け」が中心です。
・1周目の間違い直しの結果、2周目の正答を目指して内容を確認。
・特定教科や特定単元に明確な弱点があった場合、次に何をすべきか計画立てる。
1周目の勉強の成果を振り返って自分のやるべきことが明らかにしてからが、
テスト対策の本番です。
「点数アップの本番は2周目から」という話をよくします。
そのため、直前土日対策までに1周目が終わるように学習を進める必要があります。
今回の井田中生の取り組みを見ると、
ふだんの声かけをしっかり守り、おおむね教材を順調に進めている様子でした。
2周目の目標は基本問題を徹底的に完成すること。
・問題を見て、答えを出すまでの流れをすぐに思い浮かべることができるか。
・問題の状況分析がすばやくできるか?(問われているものは?設問の状況や条件は?)
最終目標はマルがつくことではなく、「スピーディーにマルがつく」ことです。
素早さは基本事項への深い理解が不可欠となります。
大きな差が出るポイントのひとつです。
ここまで対策が進めば、基本問題の対策はひとまずクリア。
残すは応用問題や読解・作文問題などへの対策です。
対策中に出た質問はほとんどが応用問題に対してのもので、
基本の理解がうかがえるものばかりでした。
ある生徒は前期期末のとき、
「この単語はどんな意味でしたっけ」
と基本レベルに対する質問にとどまっていました。
ところが今回は、
「how to も the way も 『方法』という意味なのに、なぜこの問題は how to ではいけないのですか?」
という芯をとらえたレベルの高い質問になっていて、それがとても印象的でした。
対策の順調さがうかがえるいい質問だと感じます。
井田中以外の生徒は今週末です。
しっかりとテスト対策を進めましょう。
小学生から中学生くらいのお年頃だと、
自分の気持ちと実際に出てくる言葉がズレてしまうことが多いです。
「(好きなのに)あんなの別にどうだっていいし!」
「(楽しかった映画のあとで)なんか長くね?もう観なくていいや」
素直な気持ちの発露は恥ずかしいと思い、どうしても斜に構えた発言をしてしまう。
自分の幼さ(幼いというイメージ)を脱ぎ捨てて、
早く大人になりたいと焦る気持ちもあるかもしれませんね。
そういった斜に構えた言動が多いほど、
じつは内心ではよっぽど気にかけているというケースが多いように感じます。
ですから、
「今日の社会のテスト、勉強してないし、もういいや」のような言動があった場合、
私はそれがその子の本心とはとらえないようにしています。
「つまり、この子にはやる気が無いんだな」と、
子どもの内面を決めつけて批判するべきではないと考えます。
「本当は社会のテストのことをだれよりも気にしているのかもしれないな」
ということもあるでしょうから。
とはいえ、この言動を黙認するべきでもありません。
はじまりは本心ではなかったとしても、
言動を繰り返しているうちに、
本当に「やる気が無い子」へとマインドセットが進んでしまう危険があるからです。
言葉の持つ恐ろしさだと思います。
私は「そういう言葉は言うべきではないよ」と諫めつつ、
小学生や中学生の授業中には
「楽しい?」と時々聞いて回っています。
はじめて聞く子にはたいてい首を振られます。
続いて、私からの圧力を感じてイヤイヤうなずく子が現れるのがお約束です(笑)
でも日々くり返していると、素直に「楽しい」と言える子が出てくるんですよね。
正解率が高い基本問題に対して全5問満点をとれたとき。
正答率の低い難問を正解できたとき。
「そんな方法があるのか!」と感動してしまうような鮮やかな数学の解説を聞いたとき。
「どう?楽しいでしょ」
特に高校受験のプレッシャーが大きいうえに、
思春期で素直さを出しにくい中2、中3あたりの子には、
喜ばれることが多い取り組みだと手ごたえを感じています。
不正解を連発したときはイヤだなという気持ちも生まれてくるでしょうが、
それを「そんなこと言っちゃだめだよ」と叱られるよりも、
「楽しい」で上書きされるほうがお互いに気分が良いですよね。
そういったポジティブな明るさのもとで勉強をしたい子が大半なのではないかなと思うのです。
「勉強を楽しいと思ってもいいんだ」
そう考える子が一人でも多く増えてくれるといいですね。
今回のテーマは「基本問題」です。
「基本=簡単、応用=難しい」と思っている方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。
辞書によると「基本とは、物事が成り立つ根拠となる重要なもの」とあります。
つまり「基本=重要なもの」
難易度の尺度はそもそも含まれていないんですね。
むしろ多くの場合、基本を身につけるにはかなりの練習が必要であり、基本を難しく感じるのはのは自然なことだと言えます。
■基本と応用の関係
応用問題にはA、B、C…と段階がありますが、どんな応用も必ず基本の上に積み重なっています。
基本が定着していなければ、応用をいくら練習しても安定しません。
「基本を磨く」という言葉はあっても「応用を磨く」とは言いませんよね。
基本を深めることで初めて応用A、B、Cに広がり、そこからさらに発展した応用Dや、応用B・Cを組み合わせた新しい応用Eへと進化していくのです。
ここが勉強の楽しさの一つといえます。
■レベルと重要度
問題集には「星2つ=中堅校合格レベル」「星3つ=難関校合格レベル」といった表示があります。
中堅校を目指す子にとって、応用DやE(星3つレベル)は必須ではありません。
しかし「基本」なくして星2つにも届きません。
だからどのレベルを目指す子にとっても、基本の徹底は避けられないのです。
難関校を狙う子にとっても同じ。
難問ばかり解けるようになれば合格できるわけではなく、必ず「落とせない基本問題」「星2つレベルの問題」が出題されます。
基本ができていなければ、どんな学校であっても合格から遠のいてしまうのです。
■よくある相談と答え
「難関校に合格したいので、応用問題重視で勉強したほうがいいですか?」
そんな相談をよく受けます。
もちろん、挑戦する姿勢自体は素晴らしいことです。
ただし応用DやEに取り組む前に、基本がきちんと定着しているかを必ず確認する必要があります。
応用を進めるのは、基本の徹底があってこそ。
焦らず、確実に土台を固めることが結果的に近道になります。
■まとめ
基本の習得に必要なのは「量」です。
計算であれば正確性とスピード。
語句や漢字であれば確実性。
丸がつくことがゴールではなく、「自在に使える状態」にすることが目標です。
どのレベルを目指す子にとっても、基本は徹底的に追求してほしいと思います。
-----
・基本=簡単ではなく「基本=重要」なもの
・応用はすべて基本の上に積み上がる
・レベルを問わず、合格のカギは基本の徹底
・基本は「量と正確性」で身につく
・自在に使えるまで磨き上げて初めて応用につながる
-----
動画では事例も交えて解説しています。
詳しく知りたい方はこちらからご覧ください!
https://youtu.be/6lDuSwo1Bss

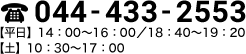

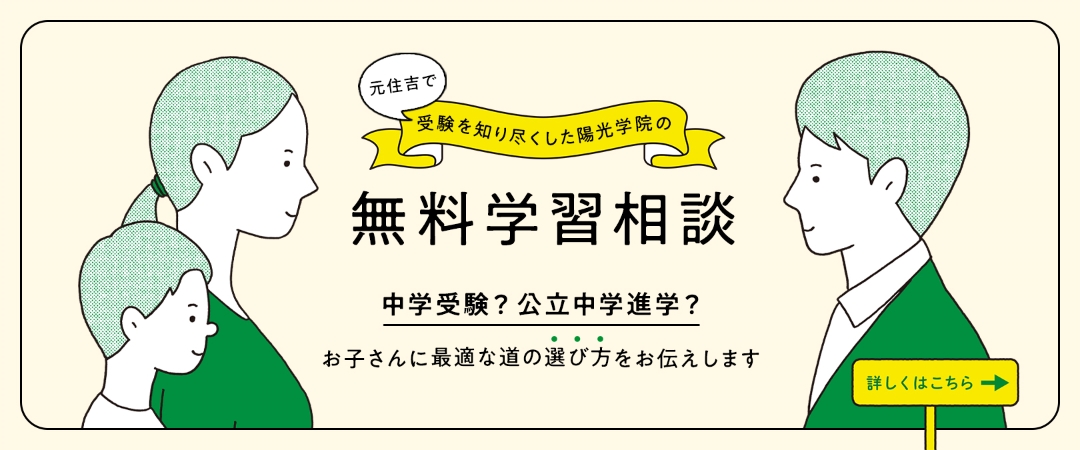

 ありがとうございます!
ありがとうございます!