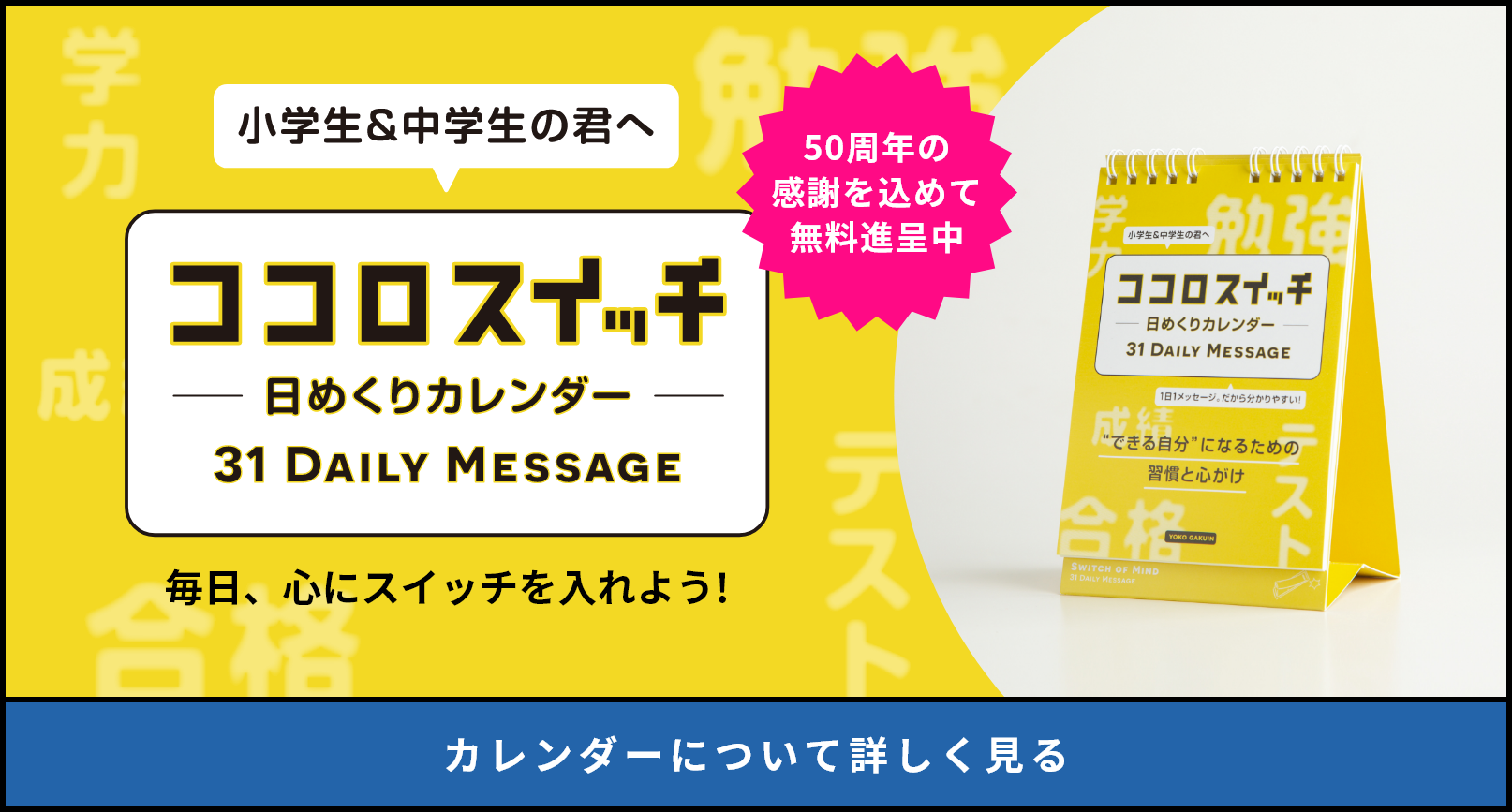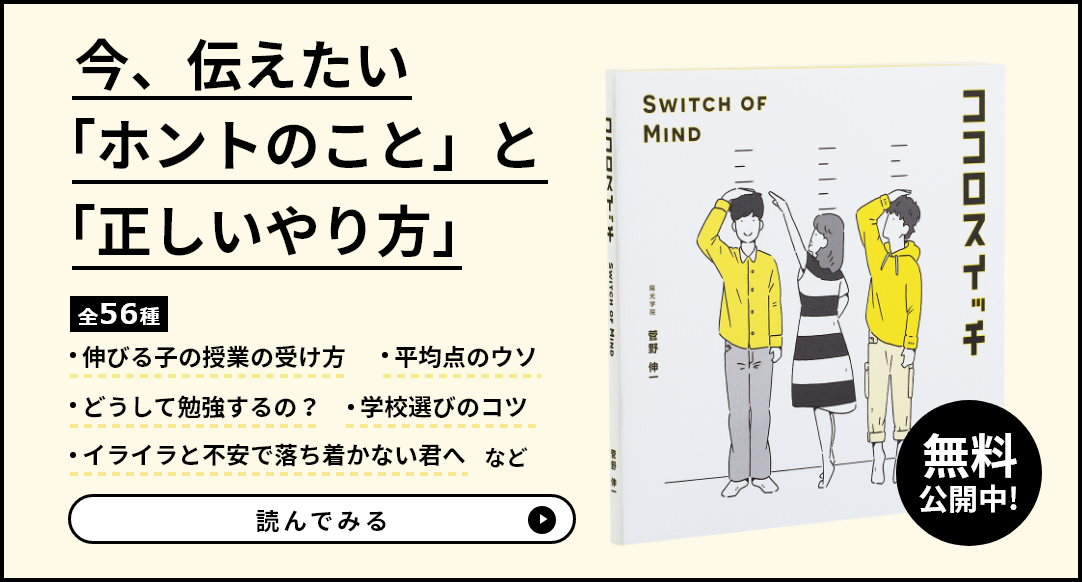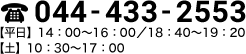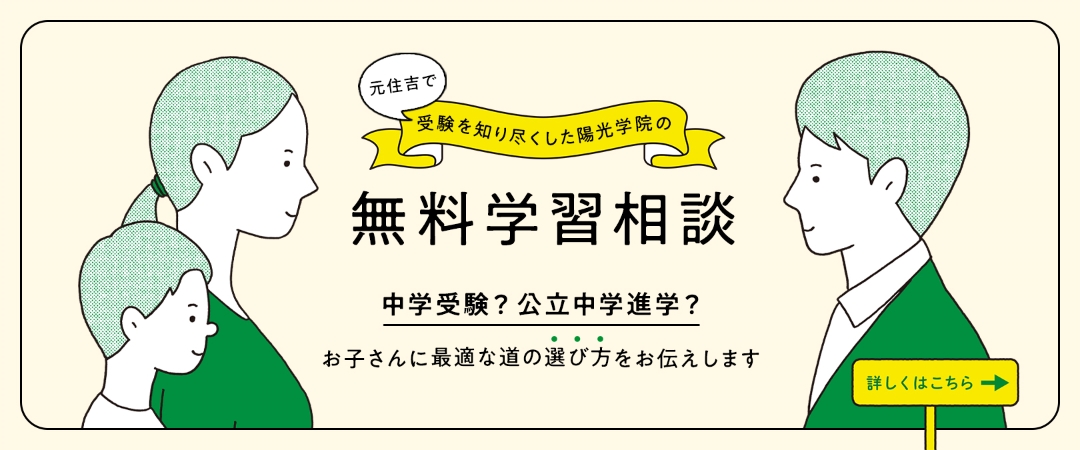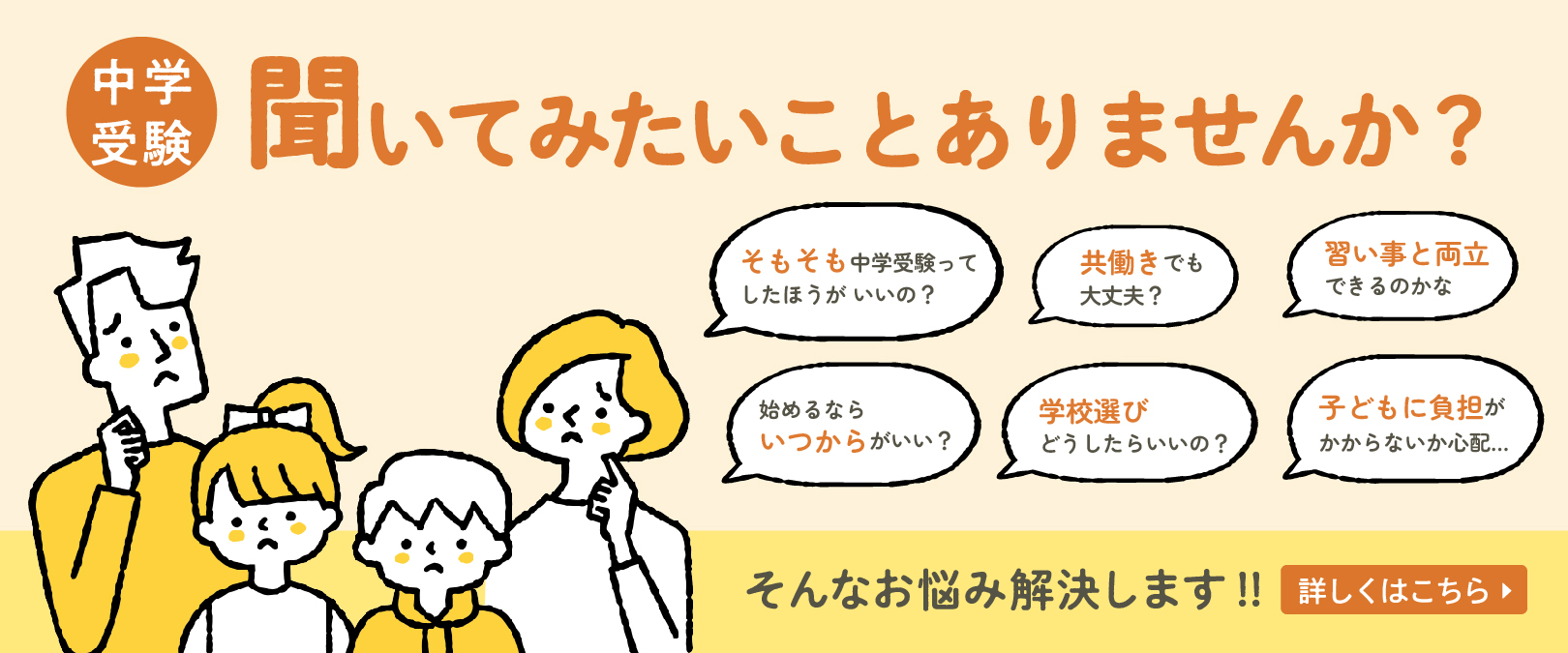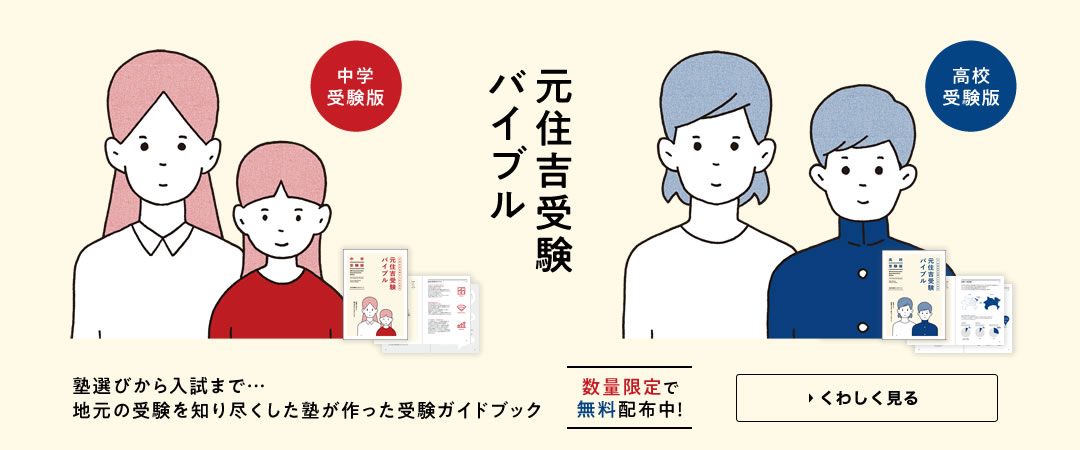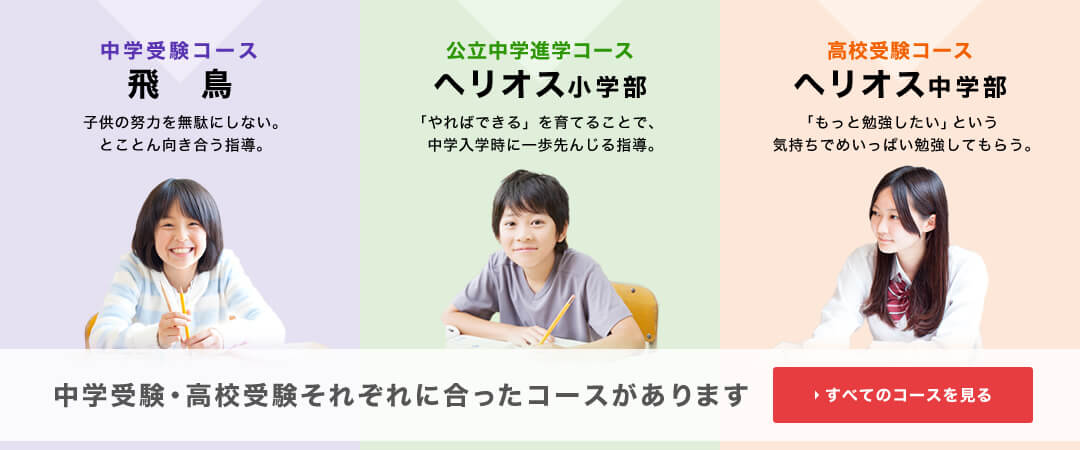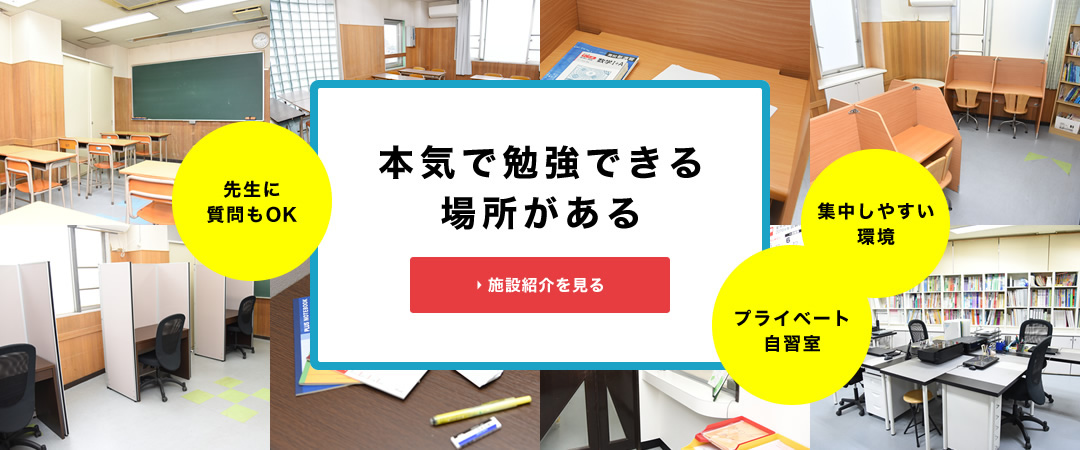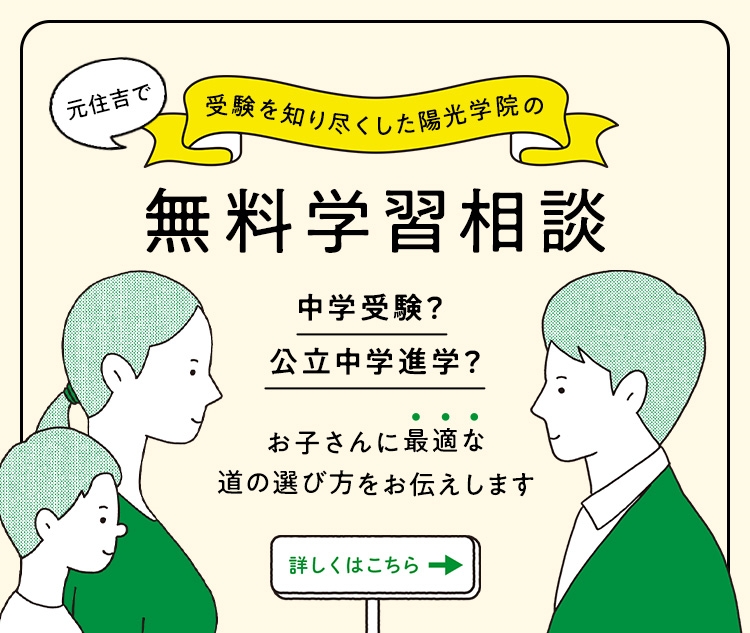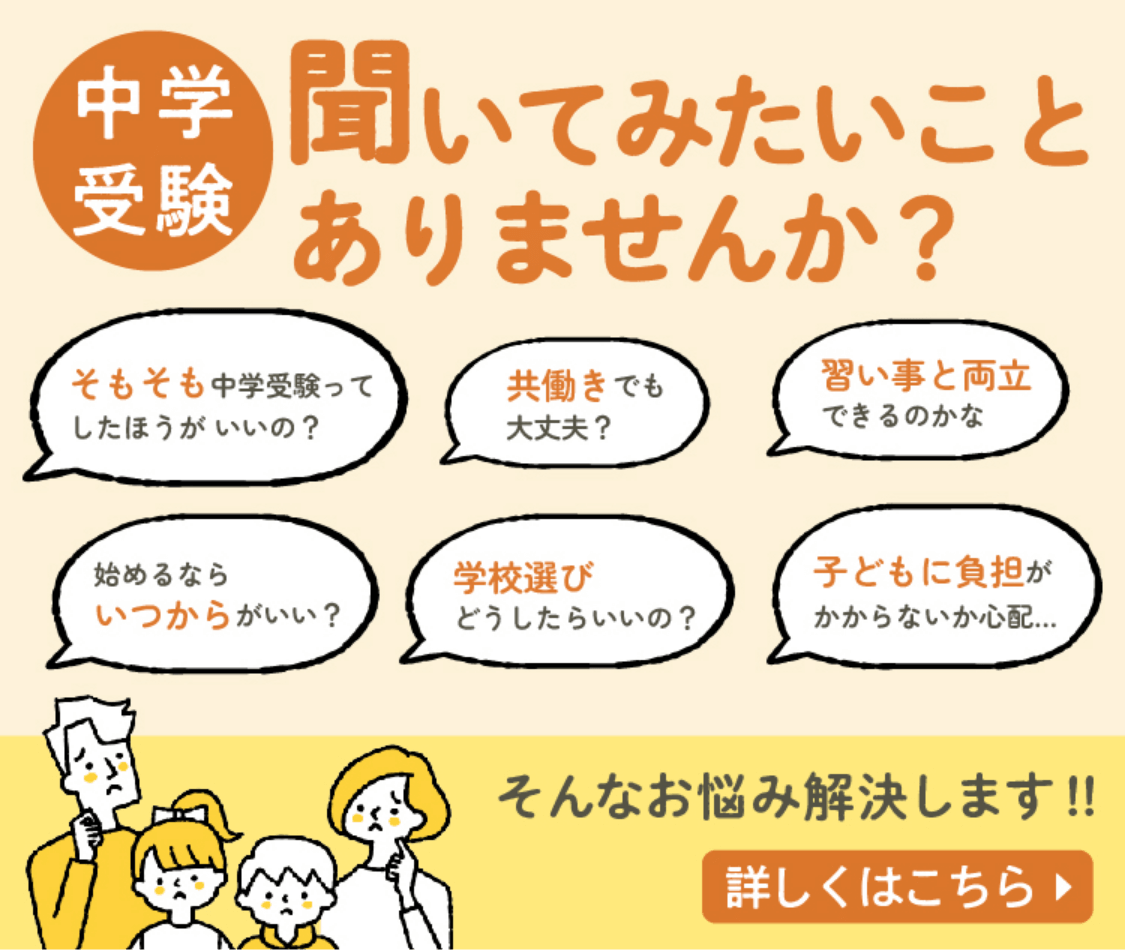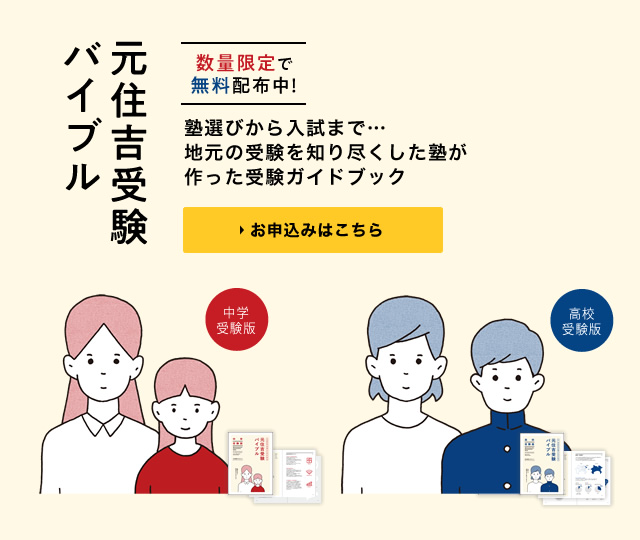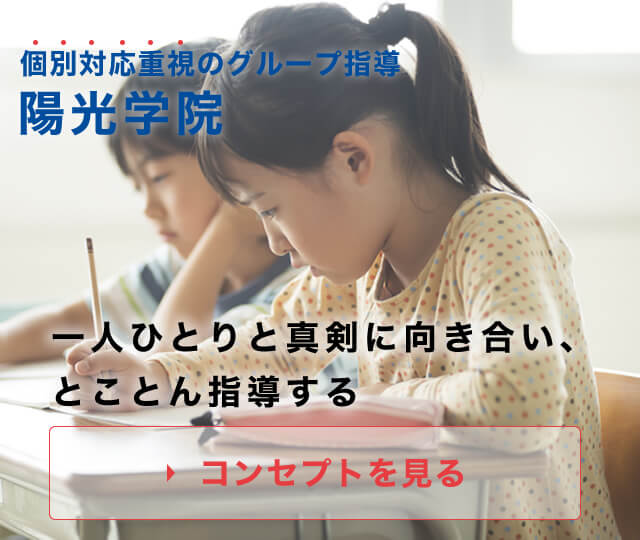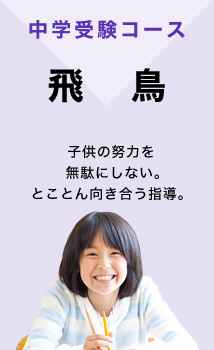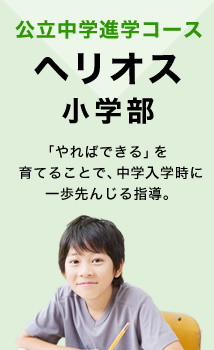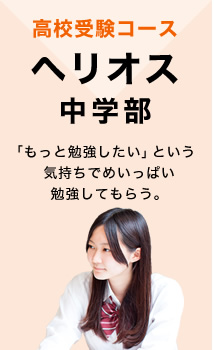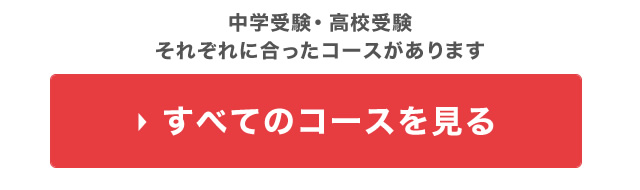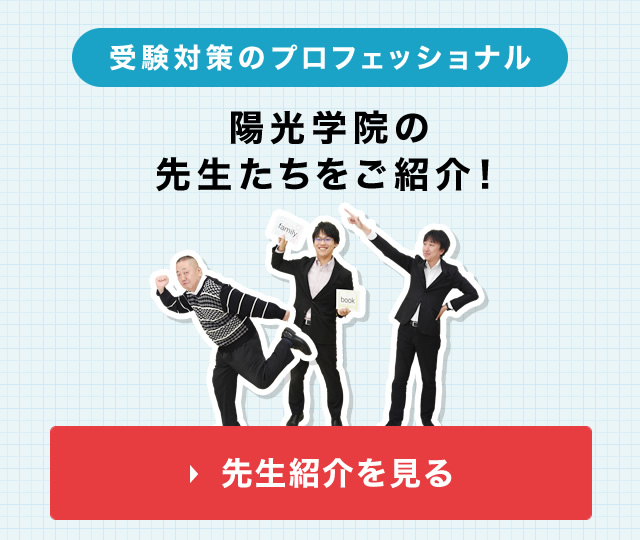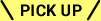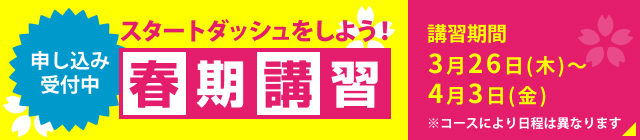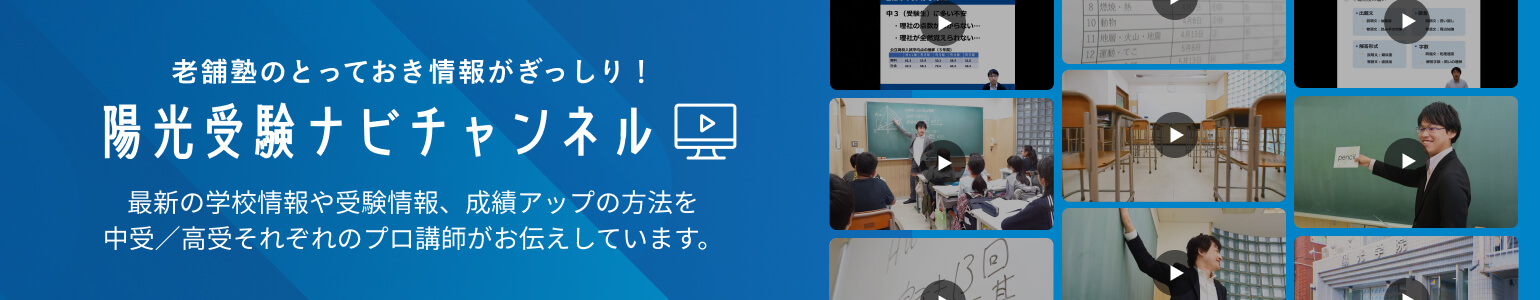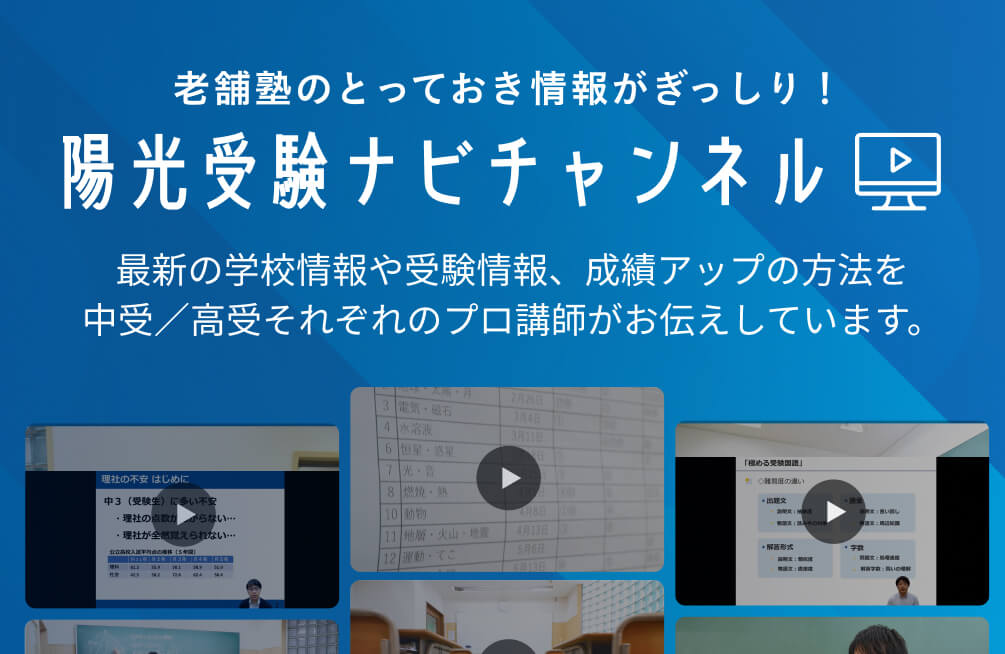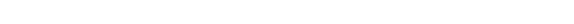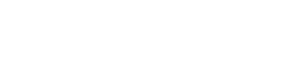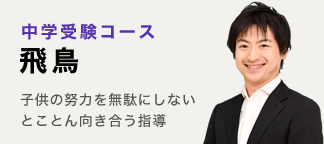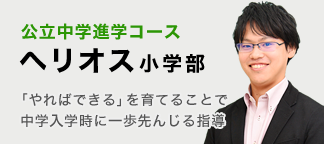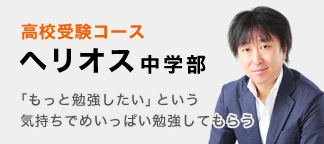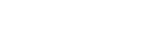- 中学受験ブログ(飛鳥コース)
-
-
【2026 中学受験合格校 (2回目)】
頌栄女子 逗子開成 三田国際
法政第二 中央大学横浜 世田谷学園
大妻 獨協2名 鎌倉学園
成城 田園調布学園 関東学院3名
女子美術大学付属 品川女子2名
品川女子(算数)普連土学園 森村学園
多摩大学目黒(特待) 多摩大学目黒(特進)
横浜女学院 かえつ有明 神奈川学園6名
文教 八雲学園3名 関東学院六浦
立正3名 実践女子学園 捜真女学校2名
目黒学院合格おめでとうございます!
本当によくがんばりました。
大逆転の合格がいくつもありました。
数年間にわたる大きな努力の成果です。
-
- 高校受験ブログ(ヘリオスコース)
-
-
【テスト後も気を抜かずに】
中1・中2は後期期末テスト週間、大詰めです。
中学によって1週間ほどの日程の差が生まれます。
今週がテストという学校も多いのですが、すでにテストが終了しているという生徒もいます。後期期末テスト終了後、一部の教科ではテストの振り返りが課題になっているようです。
テストが終わっても中2後期成績のためにできることはまだまだあります。
気を抜くわけにはいきませんね。
学校の課題は塾に持ってきてくれれば相談にも乗りますし、添削もできます。
そもそも提出物の質を少しでも高めたいということは、内申だけが目的ともいえないはずです。
とはいえ、内申が一番の関心事であるのならば、取り組むべき時にきちんと取り組む必要はあります。中2後期の内申は135点満点中の3分の1を占めます。
これは受験への意識がいまよりも高くなったとき、振り返るとほとんどの人が後悔してしまう魔の評定です。
やらなかったことへの後悔は重たくのしかかってきます。ところで、ほとんどの中3生は昨日をもって高校入試を終了しています。
つまり、現中2生は本日から「受験生」です。
今この時期の取り組みが受験生としての最初の後悔にならないようにしましょう。
-
- 頑張る気持ちを引き出してくれました。
- 目標に向かって頑張る力が、大きな財産になりました。
- 親としては「任せておけば大丈夫だ」と安心でした。
- 「合格するかではなく楽しんで勉強しよう」と声をかけてくれました。
 施設紹介を見る
施設紹介を見る