小5英語では英語の暗記が進んでいます。
金曜日の授業ではプレテストを行い、水曜日の単語テストで完成を目指します。
毎週の新出単語である10問と、
前週の10問も合わせて出題するため20問。
都合、同じ単語が日をまたいで4回出題されることになります。
出題数を抑えた入門用の単語テストを始めたのが8月。
その頃と比べると次の2点で大きな成長を感じます。
1.単語は、書かないと覚えられないという認識が「当たり前」になった。
2.単語のつづりルールについての「当たり前」が広がっている。
1.認識について
英語の授業は水・金ともに1時間目。
私が教室に入室すると、多くの子が単語帳を開いて準備をしています。
直前ギリギリまで書いて練習している子の姿、
さらに、家庭でたくさん練習を繰り返してきたことが分かる練習用紙も目にします。
テストの前としてとてもいい雰囲気です!
2.つづりのルールについて
英単語の練習をはじめた頃、既習の知識に基づいて書ける単語は
「ピアノ(piano)」「バナナ(banana)」など、つづりがローマ字と直結しているものばかりです。
「オレンジ(orange)」「セヴン(seven)」でさえも、謎のeや予想外のaが紛れ込むため、つづりの間違いに納得ができないという子も。
しかし練習は進み、英単語のつづりの経験が蓄積されたことで
「英単語あるある」に触れる機会が多くなっています。
「ジューン(June)」最後のeにさえ気をつければ大丈夫そうだ。
「サンデイ(Sunday)」最初のサが「sa」ではなく「su」になるのはよくあることだ。
「サブジェクト(subject)」サ(su)、ブ(b)、ジェ(je)、ク(c)、ト(t)。あ、そのままだ!
このように「当たり前」が広がってくると英単語の暗記に勢いがつきます。
「lエル」と「rアール」、
「er」と「ar」、
busyやhourのような特殊な読み方の英単語も今後出会うことになります。
エルとアールは日本人の永遠の課題かもしれません…。
効率良く単語の暗記をするためには、
努力することにタイパやコスパを求めすぎないことも大事です。
その週の単語を書ききる努力こそが、
当たり前を広げる最短経路です。
国語の文章問題(点数状況や○×)が不安定な生徒は、解き方を曖昧にしているケースがほとんどです。
特に誤答を生みやすい以下の8つをチェックしましょう。
- 内容面で設問に対する応答になっているか
- 文法面で設問に対する応答になっているか
- 設問の条件を満たしているか
- キーワードをすべて含んでいるか
- 対象の無い指示語を使ってはいないか
- 余計な語句は含まれていないか
- 文法上の誤りはないか
- 誤字脱字はないか
- 内容面
「喜んでいる太郎の様子がわかる一文を答えなさい」の場合、
・喜んでいることが伝わるか。
・太郎のことになっているか。
・様子を記述できているか。
- 文法面
「『~が重要だ』に続く形で答えなさい」の場合、
「お年寄りに席をゆずる」と答えても、それでは「~が」につながらない
「お年寄りへの気配り」と答えれば、「~が」につながる。
- 設問の条件
「○○字以内、ここよりあと、第三段落の中から」など。
いくら二十字以内だからとはいえ、七字~九字では答えに適さないケースがほとんど。
その場合はキーワードがたりないと考え直すべき。
- キーワードをすべて含んでいるか
「○○を含んで」と明言されている場合もあるが、筆者の主張に沿えば答えに含めるべきキーワードがおのずと浮かび上がってくる。
- 対象の無い指示語
「これがお年寄りへの気配りだということ」
これって何?
- 余計な語句
指定字数(~字以内)があると、余計な(入れなくてもいい)語句を入れる猶予はない。
キーワードを全て含め、かつ過不足の無い記述が答えの理想形である。
- 文法上の誤り
「私はサッカーが好きで、彼は野球だ」など文になっていないものはダメ。
- 誤字脱字
漢字間違いはもちろん、「てにをは」違い、「ら」抜き、「い」抜き など。
また書き抜きのときは「楽しいこと」「たのしい事」のような漢字仮名混じりにも要注意。
これらをセルフチェックできると、バツをもらう前に自ら手直しができます。
記述問題は答えを出した段階では、本人が自信満々だということもめずらしくありません。
もし誤答ならばその理由をはっきりさせないと不満が高まり、国語嫌いになっていきます。
「算数と同じで、国語の解き方にも答えにもちゃんとルールがあるんだな」
と思ってもらえるのがスタートラインです。
中3の日曜授業は毎回10:00~16:15の日程です。
3教科はテスト形式の実施、宿題の2教科と合わせて5教科を解説します。
先日(12月7日)は4回目でしたので、特に15時ごろの集中力は以前までの回と比べると維持できているように思えます。
初回(11月16日)は笑ってしまうくらいみんな疲弊しきっていましたからね 笑
また、「朝から実施」というのも入試本番を考えたねらいの一つです。
一握りの例外はありましょうが、高校入試はすべて午前の開始です。
神奈川全県模試も午前10時の開始です。
午前中に力が出る練習&習慣化を意識しています。
先週、今週はグンと寒くなってきましたね。
布団から出るのもつらいと思います。
でもそこで布団から出なければいけないのも受験生としての責務です。
受験が終わったら、日曜日の朝の過ごし方は好きに決めてください。
でも受験のその日までは、寒さに負けないで頑張りましょう。
近隣の学校からインフルエンザの学級閉鎖が少なくなったのは、ひとまず安心ですね。
それでも感染症対策は万全に。
第2波、第3波はご勘弁です…。
英文法の難しさ。
I ( ) Japan since I came here five years ago.
(5年前に来て以来、私はずっと日本にいます)
- have been in 2. have been to 3. has been in 4. has been to
この問題の答えは1. have been in なのですが、
やっかいなことに have been to = ~へ行ったことがある
という重要イディオムがあります。
ですから、2. have been to を選んでしまう生徒も多いんです。
とはいえ、基本問題(=大切だということ)であることは確かな問題です。
そのためか、問題集の中には解説無しということも多く、
解説があったとしても、「have been in ~ = ~にずっといる」の一文に留まります。
解説することがそれしかないと言われてしまうと、
その通りかもしれません。
入試英文法を攻略する際に大事なことは、
「自分の答えのどこが間違っているのか」を理解すること。
あるいは「どう考えれば誤答と正答を見極められるか」を学ぶことです。
have been to は 類似イディオムと混同していますよ、とか。
have been in は現在完了の継続用法、have been to は経験用法に対して頻出であるから、
まずは現在完了の用法を見極めましょう、とか。
自宅学習だと、間違え方に寄り添った解説が受けられないのが英文法の難しいところです。
この問題の場合、2, 3, 4 の誤答それぞれに対して的確な解説は変わってきます。
ですから英文法に関しては、先生に尋ねながら解説を受けるほうがよく伸びます。
英文法は一般化と具体化の線引きがとても難しい分野。
英文法という「法」はあるけれど、例外も多くて見極めが困難です。
英文法に関しては遠慮せずに、
「どうしてこれが間違いなんですか?」と探求する視点をもつことが大切なんです。
中1・中2の定期テスト対策が大詰めです。
今週は近隣の多くの学校で定期テスト本番となります。
中2の数学は約2週間でテスト範囲の基本問題を2周仕上げました。
「問いを見て解き方がすぐにわかる状態」になるまで問題に打ち込み続けています。
対策期間中は平日も土日対策も関係なく、数学の始めは確認テストから始めています。
私が注意するのは解いているときの様子。
本人の視点だと、マルかバツかは明らかにできますが、
その途中の姿については自分では振り返りにくいし、自己評価も難しいところです。
そこは先生に見てもらうのが一番です。
基本問題には王道の手順があります。
練習では手順を覚えて動き方を刷り込み、
テストでは覚えた手順を引き出す。
設問文やグラフなどに目を通してから、数秒以内に計算を始められるかが勝負です。
(例)1次関数の問題
1(初手).座標が2点与えられていれば、すぐに変化の割合を計算できる。
2.変化の割合を計算したらy=ax+bの式に落とし込む
3.座標を代入しbの値を求め、再びy=ax+bの式に落とし込んで終了。
初手に対して3秒以上ペンが動かない時間が続くのであれば、
それは基本の定着がまだまだである状態。
テストではマルがつくこともあるかもしれませんが、
自信をもってマルが付くことを見込める段階ではないということです。。
「たまたま正解するときもある」では自信につながりません。
思うように勉強が進まない辛い時間となってしまう前に、基本を叩き込むのです。
基本の完成は数学を楽しむための重要要素でもあります。
やっぱり数学の授業もテストも楽しんでほしいと思います。

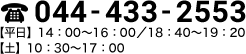

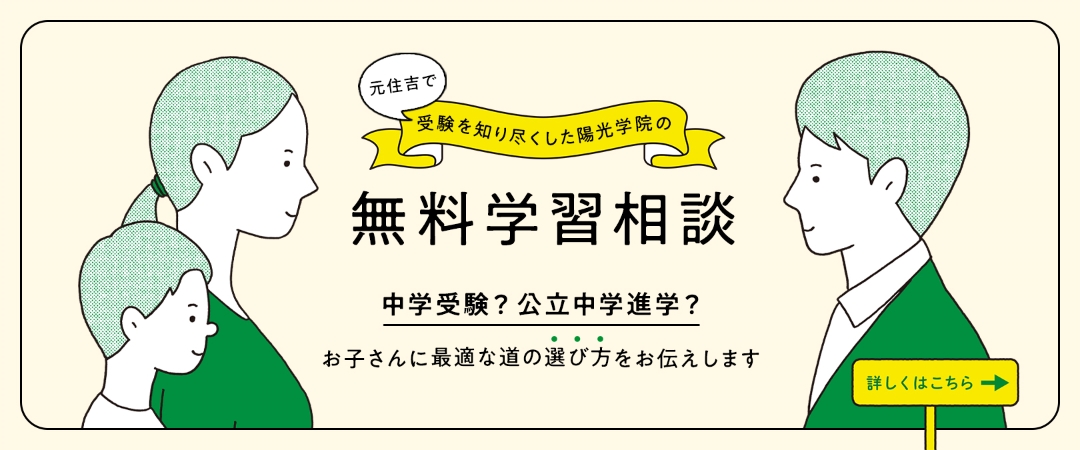

 ありがとうございます!
ありがとうございます!