小学4年生クラスの授業でのこと。
ある生徒が「僕は計算は得意だけど、角度の問題が苦手だ」と言っていました。
問題を解くのを見ていると、一周=360度、一直線=180度というのはまだ身についていないという状況。
ですから、55度と75度と言われた瞬間に、たし算をして130度になるか、ひき算をして20度になるかの二択しか思いつかない。
図中には書かれていない180度を計算に使うなんて思いもよらなかったことでしょう。
しかし、その生徒のすごいところは180-55とか、360-75を絶対に間違えないんですよね。
冒頭の「僕は計算は得意だけど」の言葉に偽りなし。
計算式さえ立てられればあとは大丈夫!と思えることは算数に対する自信につながるはずです。
国語でも漢字について得意なことがあったり、
文章を読むことが得意だったり、いくらでもあります。
高学年になるにつれて何かがひとつ欠けているだけでテストの点数に結びつかなくなるということもありますから、
その一つの欠けのせいで全体に向けて自信をなくしてしまいがちです。
でも、それはとてももったいないことだと思います。
あともう少しの要素をクリアすれば、一気に点数が伸びる瞬間が目の前にある。
そう考えてもらってワクワクしてほしいのが私の気持ちです。
得意なことを1つでも持って、それを練習することを忘れないでくださいね。
高校入試が終わり、高校英数講座がスタートしました。
高校生の準備として、英語と数学について高校の学習内容を指導します。
初回の授業ではガイダンスとして高校の勉強に必要なことを話しました。
私が大切だと思う厳しいことを話したので、多少語気が強くなってピリピリしてしまいましたが。
このたびの高校入試で多くの子たちが痛感したであろうことは
「1年生の勉強をナメてはいけない」ということでしょう。
・中学1年生は「基本」
・基本とは2~3年生の土台になる「大事」なこと。
・基本の習得は、えてして「難しい」
これらのことがあるから、3年生になって1年生の勉強に泣かされたという子がほとんどなのです。
とはいえ、彼らだって1年生の頃に手を抜いて勉強していたわけでもないと思いますよ。
しかし中3レベルの勉強を経験して、「中1のときはナメていたかもしれない。自分はもっとやれたはずだ」という後悔になる。
大切なのは、この失敗をくり返さないことだと私は考えます。
・高校1年生は「基本」
・基本とは2~3年生の土台になる「大事」なこと。
・基本の習得は、えてして「難しい」。しかも中学生の何倍も「難しい」。
そこで、中3生に伝えたいのは「高校1年生の勉強をナメてはいけない」ということ。
とくに高校生の勉強は「自ら学びに行く」というウエートを高く持つことが大切。
「教えてもらうまで勉強が進められない」ではなく、状況を自分で打開する姿勢が欠かせないのです。
主体的に学習に取り組む態度が高校入試において他の観点よりも重視されている(第二次選考)のも、ここに理由があると考えられます。
高校入試があったことでかけられた魔法が解けてしまったなんてことにならないように。
高校生から先、自分を変えられるのは自分だけです。
中1・中2は後期期末テスト週間、大詰めです。
中学によって1週間ほどの日程の差が生まれます。
今週がテストという学校も多いのですが、すでにテストが終了しているという生徒もいます。
後期期末テスト終了後、一部の教科ではテストの振り返りが課題になっているようです。
テストが終わっても中2後期成績のためにできることはまだまだあります。
気を抜くわけにはいきませんね。
学校の課題は塾に持ってきてくれれば相談にも乗りますし、添削もできます。
そもそも提出物の質を少しでも高めたいということは、内申だけが目的ともいえないはずです。
とはいえ、内申が一番の関心事であるのならば、取り組むべき時にきちんと取り組む必要はあります。
中2後期の内申は135点満点中の3分の1を占めます。
これは受験への意識がいまよりも高くなったとき、振り返るとほとんどの人が後悔してしまう魔の評定です。
やらなかったことへの後悔は重たくのしかかってきます。
ところで、ほとんどの中3生は昨日をもって高校入試を終了しています。
つまり、現中2生は本日から「受験生」です。
今この時期の取り組みが受験生としての最初の後悔にならないようにしましょう。
中3の面接練習が始まっています。
必ず問われる志望理由をはじめ、頻出の質問に対する応答内容を練っていきます。
「志望理由」
まず、高校で行われている取り組みの実際を調べ上げ、興味をもったり惹かれたりしたことを考える。
たとえば部活動加入率、文理選択、大学進学のフォローの具体的な内容など。
自習環境を挙げるケースが多いが、それなら自分自身はその自習環境をどのように活用するつもりなのかを考える。
(自習室を挙げておきながら、進学後「自習室を使うことがありませんでした~」では寂しいですものね…)
その他、説明会や見学会などで聞いた話や感じたエピソードがあるとよい。
「教科の活動」
得意教科や苦手教科に対して、意図して努力したことを考える。
それを高校進学後にどう発展させていきたいかという考えをもっておくとよい。
苦手科目があることそのものは何も悪いことは無く、苦手を苦手なままにさせたくないという思いが心象をよくする。
「教科外の活動」
「どんなこと」をやったかを伝えることはもちろんで、
その活動で感じたこと、大切だと思ったことをまとめる。
上記と同様、高校進学後の展望に結びつけたい。
「高校卒業後の進路についての考え」
今の時代は大学進学を見すえているケースが多いので、
大学(学部)の希望や、将来の職業についての考えがあるのであればまとめておきたい。
その際には、学部ではどんな4年間を過ごすのか、希望の職業に就くにはどのような努力を重ねるのが一般的なのか etc…
事実ベースで知るべきことを調べておけば具体性がグッと増す。
面接練習を進めていくと、その生徒が学校に求めているものや自分が大切にしていることの軸がわかるようになっていきます。
今週に面接練習をした生徒は、話を進めていくうちに「自分の意見を論理だてて説明する力」を大切にしていることがわかりました。
この生徒の面接で話す内容の軸はそれになります。
「志望理由」、「教科の活動」、「教科外の活動」など何を話すにしても、
自分が大切に考えている軸を中心に話題を構築すれば、
結果的に、一貫したブレない考えを獲得できます。
また、緊張するのは当たり前なので落ち着いて話すことは必ずしも実現できないかもしれません。
自分が話す軸を一つや二つにしぼっておくことで
「最低限、それだけを話せばいいんだ」と、気が楽になると思います。
まとめますね。
調べられることを徹底的に調べましょう。
自分が大切にしていること=軸を定めましょう。
公立入試まで1か月あまりとなりました。
刻々と期限がせまりつつあるこの時期、あれもこれも勉強できるわけにはいかなくなってきます。
この時期は何を勉強するかという課題設定を間違えないことが大切です。
すでにある程度完成したといえる単元をこれから勉強する優先度は低いでしょう。
暗記でどうにかなりそうな単元で、知識の抜けが多いなと感じたところを補修する優先度は高いはずです。
教科ごとに合格のための目標点を設定し、勉強する科目と単元を設定するのもいいですね。
また直前期の勉強は、
残り30日は取組みから本番までの時間が短いので、暗記をしたことを忘れる前に入試本番がやってきます。
いわゆるボーナスタイム。
「じつはまだ余力があるんです…(ちょっと休憩時間が長かったり…)」という生徒も、
頑張る価値の高い時期です。
受験生の皆さん。
あと少し。
あと少しだけ、頑張ってみませんか?

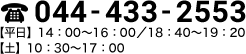

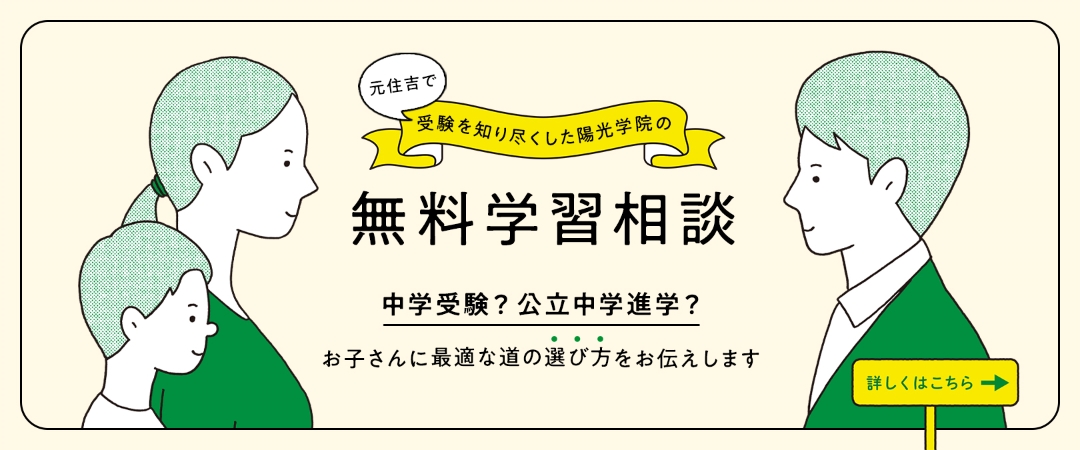

 ありがとうございます!
ありがとうございます!